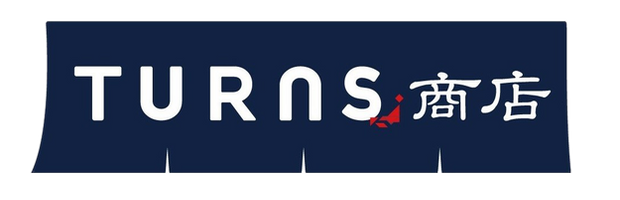張子職人に弟子入りして伝統を継ぐ|仕立屋と職人
職人に惚れ込んで弟子入りし、その生き方を伝えようと奮闘する2人組がいる。
誰のために、何のための表現をするのか。
20代のときにずっと探してきたその答えのヒントを、自分とは別世界の住人だと思っていた職人の覚悟に見出した。
▼「仕立屋と職人」の商品はこちら!
職人の「生き様」との出会いから始まった、「仕立屋と職人」
ネオンが好きなのに、東京を離れた理由
かつて街道だった面影が残る小さな宿場町に引っ越してきたのは、東京から切り取って貼ったような出で立ちの2人。引っ越して2年半が経つ今でも、彼らは彼らのままでこの町の暮らしを楽しんでいる。当初は歩いているだけで好奇の目を向けられた2人は、今では近所の人と酒を酌み交わし、祭りで一緒に神輿をかつぐ町の人気者だ。彼らがまとう空気は、この町にかろやかで新鮮な風を運んでいる。

滋賀県の北東部に位置する長浜市木之本町木之本町で、地域おこし協力隊として活動する石井挙之さんとワタナベユカリさん。二人とも首都圏で生まれ育ち、十代から東京で多くの時間を過ごしてきた。「踊るのも飲み歩くのも大好き。ネオンがない場所に住むなんて想像できなかった」。彼らが引っ越した町にはクラブも居酒屋もないし、そもそも夜は人が出歩かない。東京を離れる選択を考えていなかった彼らが、「どうしても地域が合わなければ、東京に戻ればいい」と自らの意志でこの町に飛び込んだ。地域での暮らしに興味や憧れがあったわけではない。熱量を注いで表現したいと思える対象と出会ったからだ。
20代の最後に見つけた、人生を賭けたいテーマ。彼らは「職人の生き様、仕立てます!」を掲げ、2017年に結成した「仕立屋と職人」(以下、仕立屋)の現場チームだ。メンバーは4人。職人に弟子入りして技と情熱を掛け合わせたプロダクトを制作するユカリさん、グラフィックデザインとストーリーテリングで発信する石井さん。そして現場にいる2人のアイデアから事業を組み立てる東京チームとして、プロデュースの役割を担う仕立屋のブレーン・古澤恵太さん、販路開拓を担当する堀出大介さんで構成されている。
職人といえば別世界の存在であり、伝統工芸に全く関わりのなかった石井さんとユカリさん。生まれて初めて「職人」と接したとき、仕立屋の物語が動き出した。2人が出会ったのは、福島県郡山市で300年以上続いてきた技術を受け継ぐ張子職人だ。彼のものづくりへの姿勢や受け継がれてきた歴史、何より100先を見据える生き方に、2人は触れたことのない覚悟の質量を感じた。これほど心を揺さぶられる出会いは、初めてだった。
職人の言葉に惹かれた2人は、「このかっこよさを伝えたい!」と人生を賭けるテーマを定めた。伝統工芸に縁のない若者に、どうすれば職人の生き方を届けられるのか。最初に出会った職人のもとでは、作業着を制作したり商品開発に挑んだりと、仕立屋だからできる伝え方を模索してきた。全国各地の職人と一緒に、自分たちにしかできないものづくりに取り組みたい。そう考えて福島の次に彼らが選んだ拠点が、滋賀県長浜市だ。福島でも滋賀でも、仕立屋は弟子入りから活動を始めている。

職人とともに1日を過ごし、技を学び、言葉にならない思いを受け取るためだ。その姿勢に覚悟を感じた職人たちは、工房の外であまり語ってこなかった思いの丈を彼らに打ち明けるようになる。工房とは別世界で生きてきた彼らが、職人の一番近くにいるために住む場所を変え、その思いに触れるために人生を注ぐ理由。彼らの心を最も震わせたのは、未来に願いを託す職人の生き方だ。
「なぜ表現するのか」の答えを、職人に見た
「こうありたい」と現実の狭間で
まもなく二十代を終えようとしていた数年前。石井さんは三年間のイギリス留学を経て、平日の朝に羽田空港に降り立った。
イギリスに行ったからこそ、今は日本でやりたいことがあると考えて帰国を選んだ。まずは実家に向かうつもりでいた石井さんをゲートで迎えたのは、虎柄のシャツを着たユカリさんだった。そのまま空港の屋上に上がり、ビールを片手に語らったのは「なぜ表現するのか」について─。
三十代になった現在の二人は、「お互いに、人から青臭いと言われそうな話をできる唯一の相手だった」と当時をふりかえる。同世代は会社の中堅に落ち着き、次は結婚なのか出世するのか、安定を求めて現実を歩んでいた。
一方、留学から戻ったばかりの石井さんと専門学校に通うユカリさんがいつも話していたのは、決まったルールへの疑問、仕事をとおして成したいこと、夢。表現者でありたい。
けれど誰のために、何のために。
空港で語らった翌年に「仕立屋と職人」(以下、仕立屋)を結成するまでの道のりは、自分が表現に託したいものとは何なのかを模索した日々だと言えるだろう。
二人の出会いは、大学時代にさかのぼる。石井さんはデザイナーを目指し、ユカリさんは美術史の勉強をしたくて、美術大学に入学した。同じサークルだった二人は、将来の見出し方が真逆だった。入学前から広告のデザインに憧れていた石井さんは、一直線にグラフィックデザイナーを目指していた。一方で、ユカリさんはやりたい仕事がなかったのだ。
在学中に友人に頼まれて犬の洋服をつくったとき、やりたいことが初めて見つかったかもしれないと感じた。大学を卒業後、石井さんは広告会社に入り、ユカリさんは犬の洋服づくりを仕事に選んだ。
がむしゃらに仕事に打ち込んでいた石井さんは、あるとき小さな漁村で先輩のまちおこしを手伝い始める。数千万円の予算でどこかから依頼が降ってくる東京での平日と、魚屋のおじちゃんに「起死回生の一発を頼む」と望みを託される漁村での週末。東京で制作した大型広告は入れ替わっては忘れられ、地域ではデザインが目の前の人に届いた。
そのとき石井さんが思い出したのは、大学の恩師に言われた「誰かの人生に影響するデザインをしなさい」の言葉。デザインを、誰かの人生に届けることはできるのだろうか。石井さんはその意義を追究するために、イギリスへの留学を決断した。
一方のユカリさんは、洋服づくりを続ける過程で、自分が生み出す価値に疑問と不安を感じ始める。時はファストファッション全盛期。洋服をつくって売っていたユカリさんには、世の中で当たり前とされる値段が疑問だった。洋服が量産されては捨てられる現実は悲しい。でも、自分は洋服にどんな価値を乗せられているのだろうか。技術を磨き直すべく、専門学校に入ると決めた。
この表現が、きっと誰かの未来を照らすから
自分なりに築いてきた方法も、信念もある。唯一、「心からこれを表現したいんだ」と信じられる何かが足りない。自分たちの表現を誰にどう届けるのか、まだその未来を確信できていなかったのだ。時に人生の歩みが定まらない不安にさいなまれながら、自分がどうありたいかをごまかさなかった二人。そんな彼らの心をノックしたのは、「職人」だった。
旅先の福島県郡山市で偶然出会ったのは、三百年以上の伝統工芸を継いだ張子職人。二人はその生き方に、今まで触れたことがない未来の捉え方を見出した。
ユカリ「東京では出会うはずもなかった職人の話を聞いてみたら、すっごくかっこよかった。だって、一つの技に人生を賭けているんだもん」
石井「伝統工芸の先には、ものを使う暮らしがある。つまり、職人は文化を築いているんだ、と初めて理解した。その自負を持って三百年の伝統を引き受け、次の代へと文化をつなぐ。だからこそ、どんなものをつくるのかを本気で考えていた」
脈々と継がれてきた意志を受け取り、次の世代に願いをつなぐ。自分が「こうありたい」、そして次の代に続く未来が「こうありますように」と二つの祈りを重ねる生き方。二人は初めて、今この瞬間のためだけでなく、百年先につなぐものづくりを知った。その覚悟と向き合ったとき、二人は心から伝えたいものを見つけたのだ。
職人と出会っていない人たちに、その生き方を伝えたい。こんなにかっこいい人がいるんだよ、と届けることが、きっと誰かを支える力になるから。そのために、自分たちができるものづくりとは何なのか、職人との会話から模索を始めた。

「仕立て屋と職人」立ち上げのきっかけは、作業着制作だった。福島に伝わる伝統工芸品・会津木綿を使い、和紙でありながら洗濯できる張子ボタンを開発した。
最初に手がけたのは、二人の心を震わせた張子職人の作業着だ。「お客さんから見たときにかっこよくて、自分も職人としての誇りを持てる作業着がほしい」。そんなリクエストに対して「つくりたい」と即答した二人は、制作の一歩目として弟子入りを選んだ。作業中にどこが汚れやすく、作業着に何が求められるのかを理解するためだった。職人が何をつくっているのかをいつでも説明できるように張子のボタンを取り付け、約四ヶ月を経て作業着が完成した。
もしも職人になりたいなら、そのまま弟子入りを続ける道を選ぶだろう。器用な二人は、工房への就職を何度も進められてきた。たしかに全国各地で後継者不足が叫ばれる今、自分が継げば一つの技術を残せる可能性は少し高まるのかもしれない。しかし空港の屋上から「なぜ表現するのか」の問いとずっと向き合ってきた二人は、誰のために、何のための表現をするのかをもう心に決めていた。
二人が次の世代につなぎたいのは、百年先の未来を見据えた生き方だ。作業着が完成した夜、二人は弟子入り先の駐車場で夜空を見上げていた。「タッグを組むのはここの職人だけにするのか、他の場所でもやってみたいのか、どうする?」、そう問いかけた石井さんに対し、ユカリさんは「他の場所にも行く!」と即答した。
石井さんが問いを投げかける前から、二人の心にはすでに同じ答えがあったのだろう。
これまで伝統工芸に関わってこなかった自分たちだからできる魅せ方で、届けるべき職人の思いを、つなぐべき人に伝えたい。
自分たちは「職人の職人」になりたい─。
この先にどんな道がつながるかわからない。けれど、それでも僕らは前へと進んでみよう。
そう決断し、活動の継続のためにボランティアではなくビジネスにする道を探った。客観的な視点を取り入れるべく、ビジネスに明るい古澤さんと堀出さんと一緒にチームを組んだのだ。2017年、「職人の生き様、仕立てます!」を合言葉に「仕立屋と職人」が誕生した。

自分たちが捉えた「職人」を世界に伝えたい
仕立屋が目指すものづくりは、「職人のために」ではなく「職人とともに」。
福島県の次に石井さんとユカリさんが拠点にしたのは、滋賀県長浜市だ。
長浜では二百五十年以上にわたって絹織物の産業が育まれてきたものの、和装需要の減少によって存続の岐路に立たされていた。仕立屋はたくさんの関係者にインタビューし、絹とは何かを学ぶために養蚕農家のもとで蚕から生糸までを追った。引っ越してから一年半を経て仕立屋がタッグを組むと決めたのは、輪奈ビロードを百年以上織る株式会社タケツネ。シルク100%で輪奈ビロードを織る機屋はすでに国内で数えるほどしかなく、タケツネはそのうちの一つだ。
「今までたくさん新しい挑戦をしてきたけれど、自分だけでビロードを広めるには限界がある」
と悩む先代の社長に、仕立屋は弟子入りとプロモーションビデオの制作を提案した。「これまで弟子入りを申し込む人はいなかった。自分にはできなかったことを、あなたたちに託したい」。
職人の「生き様」と、仕立屋の覚悟が重なった。
タケツネとの打ち合わせ初日、仕立屋がベテランの職人たちを前に問いかけたのは「タケツネは、百年後にどうなっていたいですか?」。何日も膝を突き合わせ、付箋と模造紙に思いを書き出した。最後の最後に見つけた心からの願いは、「百年先も機屋でいたい」。ビロードに込める意志が、一つに定まった瞬間だった。弟子入りと並行して、まずはプロモーションビデオの撮影をスタート。ユカリさんが輪奈ビロードで衣装を手がけ、一枚のビロードを織りなす技をダンスに落とし込んだ。
現在は、ビロードの特性を活かして現代のライフスタイルに合わせた商品の開発に取り組んでいる。
何百年も受け継がれてきた伝統のなかで生きてきた職人と、自分たちが歩む道を決めた仕立屋。ともに思い入れが強いからこそ、意見がまとまらないときも少なくない。現実は、二歩下がりながら泥臭く三歩進もうとする毎日の繰り返しだ。今はまだ、この活動だけで仕立屋のメンバーが十分に食べていけるビジネスになっていない。それでも彼らは「職人」という生き方を届ける道を進み、その先にまだ見ぬ景色が拓けると確信している。
石井「ロンドンには日本の伝統工芸品を好む人がたくさんいたけれど、彼らも僕も職人を知らなかった。職人の生き方を世界に届けられたら、日本がもっと興味を持たれる国になるかもしれない。こんなにやりがいのある挑戦が目の前にあるんだから、人生を賭けてやってみたいよね」
ユカリ「私一人では三百年も生きられないけれど、三百年も技を継いできた職人だから見える世界があるじゃない? そうやってバトンを引き受けて未来につなぐものづくりを、一番近くで見せてもらえる。それが何より楽しいよね」
大きな覚悟を持って何百年分の意志を引き受ける職人と出会い、ものづくりに未来への願いを託す生き方を知った二人。
職人とともに生きる決断をした仕立屋は、自分たちの届け方で未来にバトンをつなげていく。
▼「仕立屋と職人」さんが作る商品はこちら!
<harico/TSUBOMI>
https://shouten.turns.jp/items/29425206
<harico/MIKAZUKI>
https://shouten.turns.jp/items/29303643
<harico/FUTABA>
https://shouten.turns.jp/items/29425273
<harico/KOLA>